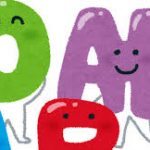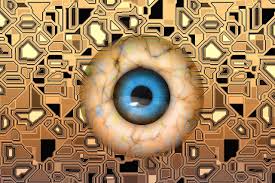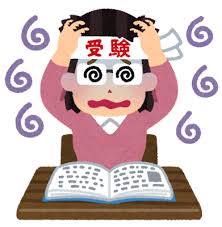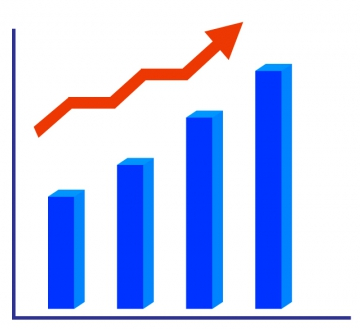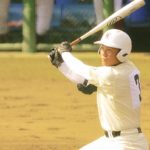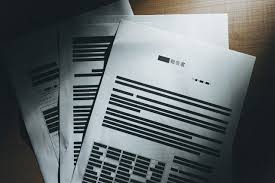目次
日本人の同調圧力は異常
日本で生活していくうえで避けて通れないのが「同調圧力」の存在です。同調圧力の正確な意味は
「特定の集団において、少数意見を持つものに暗黙のうちに多数派意見を強制すること」
です。特に日本人は「和」「調和」を重んじ、異質なものを排除する民族性があるので、海外と比べ様々な場面で同調圧力が特に強く働きます。
「一度決められたレールを外れたらそれだけで、バカにされ、就職にも不利になる」
「有給休暇や育休の制度はあるが、みんなとっていないので自分だけ取るのはためらう」
「仕事を早く終わらせても定時に上がりにくい」
「飲食店で自分だけ違うメニューを頼みたいが、ついみんなと同じものを頼んでしまう」
「大地震が起きると世間が自粛ムードになる」
「知らないと流行に遅れそうだという理由だけで興味もない音楽を聴く」
日本では様々な場面で他人と違う行動をすると白い目で見られます。いや、正確にいうとたくさんの人がいれば、そいういう目で見る人もいるということです。例えば十人が集まって、ある一人がみんなと違う選択をすると、関係のない3人くらいがそれを批判する、残りの6人は違和感を覚えながらもただ自分の希望を押し殺し、何もせず傍観しています。
情報源や価値観が少なかった以前の日本なら、もっと同調圧力は強かったのですが、今の日本人は昔と比べれば価値観が多様化し、同調圧力が弱まったように感じます。
少し話はそれますが、以前、熊本県の秀岳館高校野球部が夏の甲子園に出場した際、同校の吹奏楽部がコンクールの出場を諦めて甲子園の応援に行くという話が美談として語られるニュースが存在しました。冷静に考えれば、吹奏楽部ならコンクールに出場したいという思いの人も多かったはずで、上からの同調圧力があったことは確かです。
このニュースに対する違和感よりも、このニュースに対する世間の反応がほとんど批判的であったこと対する安心感のほうを強調します。「みんなのために」という同調圧力に騙されずに、正しく判断できる人が大部分でした。日本人の大半は同調圧力に違和感を覚えているのです。
しかし日本にはいまだに、同調圧力が大好きで、他人にも同じことを強制する人もたくさんいます。「みんなやっているから」「みんなに迷惑をかけるな」「自分勝手だ」などという反論しにくいありがちな理由を並べるのが典型的なパターンです。
同調圧力はかける人、かけられる人のいずれも不幸にする
世の中には3種類の人がいます。
- 他人に同調圧力をかける人
- 同調圧力に違和感を覚えつつも、それに従ってしまう人
- 同調圧力に屈せず、自分の頭で考えて行動できる人
もちろん同じ人が、時と場合によって変化することもよくあります。
これからの時代で最も得をするのは③の同調圧力に屈しない人です。自分の頭で考え、多数派に流されず論理的に行動します。もちろん論理的に考えた結果、多数派が正しいとわかれば多数派に従います。多くの場面で①②に当てはまる人はかなり人生損していると言えます。彼らに待ち受ける末路は以下の4つです。
- 時代に取り残される
- 人望を失う
- 思考力が低下する
- 幸福度が低下する
みんなと同じことをしていたら時代に取り残される
本当はやりたいことがあるのだけれど、まわりの目が気になるし、周囲に反対されるし、とりあえず皆が言っていることに従おうと思うのは大変危険です。
21世紀はグローバル化の時代です。自分の周り、たいていの場合、日本人のごく一部の集団の常識通りに生きていることはリスクでしかありません。世間の常識というものは5年か10年で簡単にひっくり返ります。以前は花形と言われた銀行員、商社マン、パイロット、薬剤師などの職業もこれからかなり危ないと言われています。有名な大企業に入ったら一生安泰なわけではありません。みんなが英語をやっているからと英語を勉強しても10年すれば、翻訳ソフトが出て勉強した意味はほとんどなくなるでしょう。
別に私は英語を勉強するなとも大企業に入るなとも言っていません。しっかりと自分の頭で考えた結果であれば問題ありません。いくら翻訳ソフトがあっても、外国人の女性は口説けません。好きな外国英語を字幕なしで見ることはできません。まわりに流されず明確な目標も持つことが時代に取り残されないためには重要となるでしょう。
同調圧力をかける人はむしろ少数派
先ほども述べた通り、日本人の半分以上の人は多かれ少なかれ同調圧力に違和感を持っています。そんな中で、古い考えの人が「みんなと一緒に」「みんなのために」という大義名分で個人の自由を奪おうとすれば、確実に人望を失います。日本人は自己主張が弱い傾向にあるので、はっきりとは反対せず従う人もいますが、心の中では不満を持っています。
本当に人望のある人はまわりに強制するのではなく、正しいと思うことを自分のためにします。世界のホームラン王、はかつてこんなことを言っていました。
自分のためにやるからこそ、それがチームのためになるんであって、「チームのために」なんて言うやつは言い訳するからね。オレは監督としても、自分のためにやってる人が結果的にチームのためになると思う。自分のためにやる人がね、一番、自分に厳しいですよ。何々のためとか言う人は、うまくいかないときの言い訳が生まれてきちゃうものだから。https://systemincome.com/14856
同調圧力をかける人は「みんなのために」という言葉で責任の所在をうやむやにします。もしうまくいかなくても連帯責任になるのですからただの責任逃れです。責任逃れをする人と覚悟を持って自分の仕事に集中し、言い訳をしない人、あなたならどちらについていきたいですか?
同調圧力に負けていては新しい発想は生まれない
これからの社会を生きていくうえでなんだかんだ大事になるのは、問題解決能力、創造力、コミュニケーション能力の3つです。しかし同調圧力に負けている人はそのうちの創造力を発揮できません。
反対意見を認めないような組織では、権力者の見方一つで物事が決まります。新しい意見を取り入れることも、工夫も創造もありません。もしも創造力を発揮したいならそのような組織から逃れましょう。所属する組織を変えるだけで同調圧力がなくなり、自由に創造力を発揮する例もたくさんあります。
同調圧力に負けずに自分の好きなことをやろう
同調圧力に負けて自分のやりたいことができない、字面で見ると馬鹿らしい話ですが、多くの日本人に当てはまる話です。人生は一度きりしかないのです。誰にでも自由に行動して幸せに近づく権利があります。
周りの目が気になるかもしれませんが、同調圧力を積極的にかけてくるような人は日本でも少数派です。昔と違って多くの情報、価値観、選択肢がそろっているのですから、周りを気にしすぎるのはやめましょう。